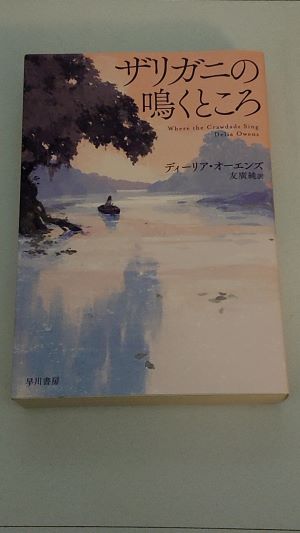こんにちは。薬剤師のHです。今回もおすすめの本を紹介させていただきます。
ザリガニの鳴くところ
著:ディーリア・オーエンズ
カイア(キャサリン・クラーク)という人里離れた湿地の小屋で暮らす6歳の少女が主人公の物語です。
暴力を振るう父親が原因で母親、兄姉は次々に家を出ていき家族はバラバラになってしまい、終にはその父親からも見捨てられザリガニの鳴くところ(茂みの奥深く、生き物たちが自然のままの姿で生きている場所)で独りで生きていくことになった主人公は、学校にも通わず、街に出れば差別を受け、飢えと闘いながらも生きていく術を身に付けていきます。
①「一匹の雌が信号を変えたのだ。その雌はさっきまで正しいチカリとジーの組み合わせを送り、仲間の雄を引き寄せて子づくりをしていた。ところが、今度はべつの信号を送り、違う種の雄を引き寄せている。二匹目の雄は彼女のメッセージを読み解き、交尾を希望している仲間だと納得してその上を飛びまわった。と、雌のホタルが不意に起き上がって彼をくわえたかと思うと、むしゃむしゃとその雄を食べはじめ、六本の脚も左右の羽もきれいに平らげてしまった。雌たちはお尻の光らせ方を変えるだけでいとも簡単に望むものをーー最初は交尾で、次は食事をーー手に入れていた。ここには善悪の判断など無用だということを、カイアは知っていた。そこに悪意はなく、あるのはただ拍動する命だけなのだ。たとえ一部の者は犠牲になるとしても。生物学では、善と悪は基本的に同じであり、見る角度によって替わるものだと捉えられている。」
②「ある昆虫の雌は交尾の相手を食べてしまうし、過度のストレスにさらされた哺乳類の母親は子どもを捨ててしまう。多くの雄たちは、危険な方法やずる賢い手で精子競争に勝とうとする。けれど、命の時計の針が動き続けている限り、そこには醜いものなど何ひとつないように思えた。これは自然界の暗い側面などではなく、何としても困難を乗り越えるために編み出された方策なのだ。それが人間となれば、もっとたくさんの策を講じたとしても不思議はないだろう」
③「雌ギツネは飢えたり過度のストレスがかかったりすると、子どもを捨てることがあるって。子どもたちは死んでも雌ギツネは生き延びられる。そうすれば、状況が改善したときにまた子どもを産んで育てられるんだって。自然界ではそういう無慈悲に思える行動のおかげで、実際、母親から産まれる子どもの総数は増える。そしてその結果、緊急時には子どもを捨てるという遺伝子が次の世代にも引き継がれる。そのまた次の世代にもね。人間にも同じことが言えるわ。いまでは残酷に感じられる行動も、初期の人類が生き延びるうえでは重要だった。その人類がどんな沼地に住んでいようとね。もしその行動を避けていれば私たちはいまこの場にいなかったでしょう。その本能はいまだに私たちの遺伝子に組み込まれていて、状況次第では表に出てくるはずよ。私たちにもかつての人類と同じ顔があって、いつでもその顔になれる。はるかむかし、生き残るために必要だった行動をいまでもとれるのよ。」
④「そのときふと、一匹の雌のカマキリがすぐそばの枝を音もなく歩いているのが目に入った。その昆虫は節のある前脚で蛾を 摑み取ってはせっせとそれを噛み砕いており、口からはみ出た蛾の羽がまだぱたぱたと動いていた。と、雄のカマキリが一匹、誇らしげに行進するポニーさながらに、まっすぐ頭をもたげて彼女に求愛しはじめた。雌も興味をもったようで、彼女の触覚が二本の指揮棒のようにゆらゆら揺れた。雄の抱擁が力強いのか優しいのか、カイアにはわからないが、彼が卵を受精させるべく交尾器を近づけていると、雌は優雅な長い首をうしろにまわし、そのまま雄の頭を食いちぎってしまった。彼自信は交尾に忙しくて気づいていないようだったが。彼が短くなった首を振って作業に没頭しているうちに、雌は彼の胸部から羽へと、少しずつ雄をかじり取っていった。しまいには雄は、頭も心臓もない下半身だけの姿になり、そこでようやく、自分の最後の前脚をくわえている雌と交尾を済ませたのだった。」
これらのシーンでは動物学の学士号、動物行動学の博士号を取得している著者ならではの生物たちの描写があり、時に暴力的で冷酷な表情を見せますが、その一方で生命力に溢れた自然界の現実をとてもリアルに表現しており、人間にもそんな一面が隠れているのだということをストーリーを通じて考えさせられる内容になっています。
機会がございましたら、ぜひご一読ください。